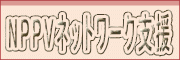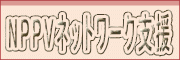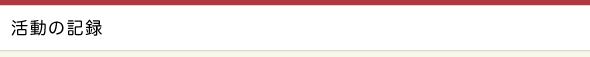 |
| ■筋ジストロフィー患者の「緩和ケア」ってなあに? |
| 国立病院機構八雲病院 河原仁志 |
| はじめに |
「緩和ケア」という言葉が混乱して使われているようにみえる。英語で言うPalliative and End-of-Life Careのことだろうか。さらにGrief
Careといわれる行為も加わるようである。
本邦では様々な疾患・状態においてそれぞれの解釈で「緩和ケア」が行われている。少なくともこの混乱は、患児・者のためになっていない可能性がある。 |
| |
私は神経・筋疾患患者とつきあいだして20年以上が過ぎた。前任地では在宅患児・者の定期的医療精査を約10年間、延べ800名以上に施行してきた1)。筋ジストロフィー(以下筋ジス)に関する書籍・ビデオ制作や厚労省の研究班などの仕事も行ってきた。そういった意味で私はいわゆる筋ジス医療の専門家ということになる。
しかし、この疾患の緩和ケアについて考えてみたがさっぱり分からない。
悩んでしまう。WHOの2002年の緩和ケアの定義では、要するに「筋ジスの診断がついた時からのQOL向上のための総合的介入」のことになる。
つまり多職種の協働作業であり、ほとんど子どもの時期に診断される筋ジス患者の場合は、特別支援教育そのもののような気もする。そこで、この原稿を書きながら今まで小児科医として経験してきたこと、今起こっている驚くべきことなどを基に、自分の考え方を整理していくことにした。そして最後にどうやったら筋ジス児の未来のためになるのか考えてみた。 |
| |
| 1.医療レベルの差が著しすぎる |
ポリオ後症候群という病態がある。小児期にポリオ(脊髄性小児麻痺)に罹患し、数十年後に運動機能の悪化をみる。わが国では1940年の終わりから1960年初頭にかけてポリオの流行があった。なぜ年月を経て症状の悪化が起こるのかはまだ不明である。呼吸機能低下や摂食・嚥下障害などは、当然生命への影響も大きく積極的な医療介入が必要になる。
しかし呼吸機能低下はしばしば見過ごされ、その結果放置され風邪や気管支炎などを契機に、急性呼吸不全つまり低酸素や高炭酸ガス血症による意識低下や息苦しさを訴え緊急入院となる。急性呼吸不全になり緊急入院した病院では集中治療室にて管理が行われ、非侵襲的人工呼吸療法(NPPV)が苦手な医師の多くは気管切開を行ってしまう。
気管切開術を受けた患者は、その後のQOLの低下に苦しみ続けることが多い。
これは筋ジス患者の呼吸不全に酷似する。
|
| |
昨秋、当院に61歳のポリオ後遺症の患者が、都内の年間収容患者数が2800名を超える救命救急センターから転院して来た。患者は急性呼吸不全のため集中治療室にて気管内挿管による人工呼吸を2週間以上にわたり受けていた。入院先では、気管切開による人工呼吸管理以外では生命の保証が出来ないという説明がされ、患者および家族が納得できないとの意思表示を行ったためである。患者、家族は都内の神経筋疾患の専門病院にも受け入れを相談されたが断られていた。
様々な患者の会に相談し、家族から当院の医師にセカンドオピニオン依頼があり、気管切開は回避可能であると考えて受け入れることになった。
当日は当院から医師2名が人工呼吸器持参で迎えに行き、挿管人工呼吸のまま先方の病院から付き添って搬送して来た。先方の病院からの付き添いは無かった。民間航空会社を利用し、8時間余りを費やして夜間にようやく当院に到着した。
その夜から、全身状態のチェックと呼吸機能の評価を行い、翌日の昼(17時間後)には抜管して鼻マスクによる人工呼吸に変え、口から食事を行い(前病院入院中は、チューブ栄養であった)、その翌日には風呂に入って嬉しそうであった。
失うことのなかった肉声にて、さかんに感謝の言葉を述べられるのが印象的であった。患者は2週間後には退院して、都内の診療所の管理で在宅にて人工呼吸を続けている。患者は障害者運動の旗手として、多くの国際会議の議長などを務めるなどの活躍を今後も続けていかれることだろう。 |
| |
神経筋疾患の多くは気管切開を行わない非侵襲的人工呼吸療法(NPPV)にて呼吸不全を治療できる。しかし、それを行える病院が限られている。つまり神経筋疾患の生命保持とQOL向上に直結する人工呼吸管理術=狭義の医療にこれほどの差異があるわけである。ここで確認したいのは、デュシェンヌ型筋ジス患者では、気管切開による人工呼吸療法は今では例外的である事実である。2005年にスイスから、筋ジス患者では、気管切開を行わない人工呼吸(NPPV)と電動車いす使用により高いQOLが保たれると声明が出ている2)。
本邦では、NPPVの技術未熟なため気管切開を行ってしまう自称専門医がいるのが残念でならない。
|
国は旧国立療養所に専門病棟を作り、筋ジス患者の長期入院を引き受けてきた。
名称は国立病院機構病院に変わったが、今も国26施設で約1600人の患者を診ている。
いわゆる筋ジス医療の専門医療機関チェーンとしての機能を有している仕組みである。しかし、そこで行われている医療・生活支援に大きな差があるらしい。
伊藤は自身の療養介護職の経験と他施設からの聞き取り調査から、食事介助の必要な人は朝のご飯が出ない施設(栄養補助食品だけで済ませている)がある、部屋の端のベッド上の患者から順次座薬を入れて一斉に病棟全体が排便を行うなどの実態を明らかにしている。
さらにケアに時間のかかる重症患者の扱いを受けている人たちは、ベッドに寝たきりにさせられざるを得ない状況である3)。
筋ジス患者のQOLの向上のためにはベッドから電動車いすへの移乗は非常に大切であり、いわゆる二次的障害による寝たきりを防ぐのは最優先の治療方針である。
患者の状態をより良く保つためのケアは医療そのものである。公的な専門医療機関と言われる施設間で、その格差が著しいとしたら大きな問題といえる。 |
| |
| |
| 2.障害児・者を囲む社会状況 |
ここに2つの新聞記事がある。昭和59年(1984)7月24日と平成17年(2005)2月21日に毎日新聞に掲載された殺人に関する記事である。
その見出しは昭和59年が「最近目立つ弱者への加害事件 新ファシズムの恐れ」、平成17年が「人命を守ってこそ福祉 優先順位の見直しを」とある。
前者は、父親が小学生を情緒障害児と決め付け絞殺する事件について書かれている。世間の同情は殺した側に集中し、殺された障害児は見向きもされなかった、とある。
後者は、難病のALS(筋委縮性側索硬化症)を患った長男の人工呼吸器を母が止めた事件について書かれており、嘱託殺人罪を適用した温情判決に、これで良かったでは片付けられないと述べている。つまり殺人を行った人への同情に関心が集まり、どうしてそんなことが起きたのか、どうやったら防げるのかの議論が不十分であることを訴えている。
さらに殺された側への関心の低さは、障害を持つ人・弱者を排除する思想が台頭する危険を警告している。これらを読み比べると障害児・者への支援は、根本的には20年間何も変わっていないじゃないかという疑問が湧いてくる。こういった社会の意識が、自分たちの行動に少なからず影響を及ぼしていることは知っておかねばならない。障害を持つ人が生きにくい社会がつくられている。 |
| |
ある特別支援学校に医療的ケア施行のための診察(その県では学校内で医師が診察することにより看護師や教員がケアを行うのを容認するようなシステムであった)に出向いた時のことである。
母と担任教師と患児が私の前にやってきた。痙性四肢まひと知的障害を合併し寝たきりであり、いわゆる重症心身障害児でてんかん発作が頻発していた。主治医からは、てんかん発作が続けば抗けいれん薬の座薬の挿肛を行うように言われており、学校看護師がそれを行うことの許可を確認するような趣旨を言われた。
子どもを診ると、突然の大きな音や触覚刺激で起こるいわゆる驚愕反応による体幹の進展と同様な姿位をとるてんかん発作が混在しているようであった。「その2つを区別しなければいけないね」と発言したところ、教師も母も不満な様子。
私は疑問に思いながらも、驚愕反応とてんかん発作との鑑別法を説明し始めた。しばらくした後で「じゃあ、どうすればいいのですか」と怒ったような母の声。睨めつける教師。私はなぜ怒られているのか分からずに困惑した。
もちろんてんかん発作の連続なら座薬を入れて中断することは必要である。しかし挿肛後は睡眠に入ってしまうことが多く、授業は中断してしまう。驚愕発作ならできるだけ刺激を控えて、授業を続けられるような環境調整が必要である。
もちろん座薬を使って眠らせることは避けなければいけない。このことは校内における教育の保障という医療的ケアの目的からして当然共有しているべき意識であると思っていた。ところが「てんかん発作だろうが驚愕反応だろうが、抗てんかん薬の座薬を入れることをお前は許可すればいいんだよ」という意味で診察を受けに来ていたことは後から関係者にそれとなく教えられた。
一部であると思うが、学校をケア付き託児所と間違うような認識があり、それにより患児の教育というQOL向上に必要な権利がないがしろにされている。以前この学会誌に医療的ケアについて書かせてもらった4)。ブームとは「中身のない記号化された消費である」という言葉を引いて、ブームの怖さを指摘した。医療的ケアがブーム化していることはないだろうか。心配である。 |
特別支援学校の生徒に掛かる費用は年間930万円/一人、地域の通常学校の生徒にかかる費用は90万円/一人と言われている5)。精密かつ個別な教育が行われているために、高額な教育費が使われていると思われる。一方北海道の高校中退生が年間3000人以上で、これは道内の高校生の50人に一人であるとの報道があった。
主な中退理由は、授業料免除の生徒数が多い学校で中退生が多いことから、家庭の金銭的困窮であろうと結論付けていた。また母子家庭で母が病気になり、高校を中退せざるを得ない生徒がインタビューを受け「福祉関係の仕事に就くのが夢なので、まだあきらめていない」と話し、放課後の教室に入れてもらっている姿が印象的であった。
私たちが生きる世の中は大きく変化している。今後はすべての事業に関して費用対効果について検証されるだろう。その中で特別支援教育を守り、発展させていくために私たちが行わないといけないことは何なのか、どう行っていくのかを考え実践する時期にきていることは確かだと思う。
社会的公正の観点から、存在価値が問われ始めている。 |
ある日の筋ジス病棟での食事風景。テレビから「派遣社員の解雇がとどまることを知らず」という絶叫にも似たアナウンサーの声が聞こえる。
次の場面では街頭で、社員寮を追い出され公園で寝泊まりする人や炊き出しに並ぶ人々が映し出される。その一方で患者が「これ嫌い」と言って箸もつけずに捨てられる食事の多さに驚かされる。それぞれが売店で買ってきた即席ラーメンに、湯を注ぎ食べやすい食器に移し替える手間を嫌がる職員の顔がある。
こういった日常の繰り返しが行われている。もし、自宅で我が子が同様な行為をしたら、叱り飛ばさないだろうか。
どうしてこんなことが許されているのだろう。前任の病院でも全く同じ状況があり、食事メニューの変更や食形態の改善などを行っても何も変わらなかった苦い経験がある。長期入院を行う専門病棟でいわゆる「普通」ではない生活が営まれている。 |
| |
| 4.彼らへのインタビューから |
筋ジス成人患者に「貴方らにとって差別者ってだれですか?」と問うたことがある。患者らとは、一緒に食事をしたり日頃からいろんな会を行ったりして、活発な意見交換をしている仲であった。
彼らの答えは「一番は親、二番目は医療者、三番目は養護学校の教員かな」という意見で一致した。その理由をまとめると、自分と関係性が深い人たちが「そんなことはしなくてもいい」「どうせうまくいかないから」と彼らを導くことへの不満のようであった。
さらに、「病名告知はいつされた?」と尋ねると、「はっきりとはされなかった。なんとなく知った」と語った。病名告知がなされず、今後の状態の変化(筋ジスは進行性に運動能力の低下する病気である)に関しての説明は皆無で、「リハビリを頑張れ」と言われ続けたとのことであった。
学校を早退して病院に通い、関節拘縮予防訓練や歩行訓練などを受けながらも、徐々に不自由になる自分の身体にいらだち、「自分の努力が足りないからだ」と思い自責の念を強めていたと驚くべき話をしてくれた患者もいた。
私たちは患者支援をしながら、彼らの可能性を奪っている。彼らを傷つけている。
今も彼らの「あれしたい、これもしたい」という要望を、患者のわがままとして処理していないだろうか。まず自分たちの行動を疑ってみることから始めなければならない。 |
| |
| 4.子どもたちの未来へ(処方箋はあるのか) |
「空から雪という白い物体が落ちてきても慌てずに対処できるのは、私たちが自然科学で雪について学習しているから・知っているからです。だから世の中で起こっていることを理解するために、経済学を学ばないといけません」と言われたことがある(中島隆信氏私信)。
筋ジス児のQOL向上のためには、やはり彼らが学ばないといけないと思う。しかし、彼らは子どもである。つまり、私たちが彼らに、何をどう学ばせるかが問題となる。
この際誰が学ばせるかは、支援する大人・社会全体と考えておくことにする。当然たくさんの人々の協働作業でなければならないからである。
|
| 何を学ばせるかは |
| ①彼らが筋ジスという病気により進行性に運動機能が低下し、そのために日常生活が不自由になる現実をどうしても理解させなければならない。 |
理解させるために教えなければならない。教えるためには、教える側が正確な知識を持たなければならない。幸い多くの筋ジスについての書籍・ビデオが世に出ている6),7),8),9),10),11),12)。
それらを利用して、有益な正しい知識を得ることができる。この場合の正しい知識とは、症状の悪化は避けられないがその進行を遅くし、できるだけ快適に生活するためのケア医療・支援が提供できるという将来展望のことである。 |
| ②私たちは子どもたちの不自由を軽減するための支援、生活を支えるケア医療を全力で行っていくことを誓わなければいけない。 |
| 覚悟を見せなければならない。なぜなら、前述した驚くべき現実は、すべて私たちの無知や自己保身などの大人の都合で続けられてきたことばかりである。もう言い訳は止めて、真正面から取り組む時期に来ている。親以外の支援者は「親の希望だから」というだけの理由で、自らの専門性を放棄するような子どもへの関わりをしてはならないと思う。 |
| ③治療効果の過小評価と過度の期待を避けなければならない。 |
過小評価は、日常生活の苦痛(精神的・身体的)を軽減するケア医療を危うくする。また最近では、遺伝子治療や再生医療による根本治療に患者・家族が過大な期待を抱くことが多い。確かに、これらの治療は科学の進歩を体感できるすばらしい成果であるが、その効果の正しい評価(患者の期待と臨床効果の差、コストパフォーマンスを含め)と治療の普及までに考えられる問題を考慮して、今できる・行っているケア医療を確実に続けなければならない。残念ながらケア医療の質に著しい差がある。
当然、高いレベルのケア医療を提供すべきであるし、それを患児の生活圏で可能にする不断の努力を怠ってはならない。これは私たち大人の責任である。また彼らを、自分から質の高いケア医療を要求する・不十分な医療に対して異議を唱えられるように育てることも、私たちの使命である。 |
| |
| 遺伝子治療やiPS細胞による再生医療などの根本治療の推進と患者のQOL向上に直結するケア医療の発展は車の両輪である。 |
| |
そのためには、本邦で提供されているケア医療の質の差を知りその質を高める努力を行いながら、根本治療の進展を待つことが必要である。正確な治療の知識を得るために、世界で現在行われている治療法をまとめて解説した米国・筋ジストロフィー親の会(PPAD)年会議報告(2007)が役立つと思われる。神戸大学医学部小児科教室の尽力により、日本語訳が手に入る。
※TREAT NMDの現状を、ドイツの患者会の方が改めて報告しています。
神戸大学小児科のホームページの表紙の下の方に「デュシェンヌ型筋ジストロフィー治療の最前線」ということで、公表されています。PDFファイルで34ページ
|
| |
| どう学ばせるかは、個々の事情により複雑になるであろう。もちろん誰が学ばせるかにも深く関わる。 |
①生活の場の選択が大きく影響する。現実的には子どもが在宅生活なのか筋ジス病棟での入院生活なのかに大別されると思われる。つまり親の管理・介護を受け地域の通常校に通う(通常の学級、特別支援学級、通級による指導)場合と日常に親がいない環境で、他人に生活介護を受け、常に医療的管理を受けながら隣接の特別支援学校に通うのかに分けて考えることが必要になる。
現状では地域の学校へ中学校卒業まで通い在宅生活を行い、高等部より転校、入院する例も多い。なぜなら、運動機能低下による日常生活介護量の増加による校内生活の困難だけではなく、心保護治療や夜間に起こり見過ごされやすい呼吸不全治療などが必要になってくるからである。
ということは、地域の通常学校(小学校、中学校)の教師と親が中心になって、筋ジスという病気について教えているあるいは、教えずに放置していることになる。
特別支援学校と通常学校の間の特別支援教育の専門性の格差は無いのだろうか?あるとすれば、それを埋める学校間の連携(特別支援学校のセンター化や特別支援教育コーディネーター)はうまく機能しているのだろうか?親は教育現場とどう関わっているのだろうか?医療者はどのようなケア医療を提供しているのだろうか?子どもが「筋ジス」の理解を進めるのに重要な思春期前後の時期に、特別支援学校はもっと積極的に関わらなければいけないと思う。
私の経験では、高等部になって編入してくる子どもの中に自分の人生に対して敗北感を持ち、自分らしい生活の確立に投げやりの態度で終始し、正しいケア医療を継続してこなかったために身体変形や心・呼吸機能低下が著しい子どもたちをみることも多い。もちろんここでもケア医療のレベル差は大変大きな問題であるが、特別支援教育の専門性が十分発揮されているとは思えない。このままではいけない。
|
①生活の場の選択が大きく影響する。現実的には子どもが在宅生活なのか筋ジス病棟での入院生活なのかに大別されると思われる。つまり親の管理・介護を受け地域の通常校に通う(通常の学級、特別支援学級、通級による指導)場合と日常に親がいない環境で、他人に生活介護を受け、常に医療的管理を受けながら隣接の特別支援学校に通うのかに分けて考えることが必要になる。
現状では地域の学校へ中学校卒業まで通い在宅生活を行い、高等部より転校、入院する例も多い。
なぜなら、運動機能低下による日常生活介護量の増加による校内生活の困難だけではなく、心保護治療や夜間に起こり見過ごされやすい呼吸不全治療などが必要になってくるからである。
ということは、地域の通常学校(小学校、中学校)の教師と親が中心になって、筋ジスという病気について教えているあるいは、教えずに放置していることになる。
特別支援学校と通常学校の間の特別支援教育の専門性の格差は無いのだろうか?
あるとすれば、それを埋める学校間の連携(特別支援学校のセンター化や特別支援教育コーディネーター)はうまく機能しているのだろうか?
親は教育現場とどう関わっているのだろうか?
医療者はどのようなケア医療を提供しているのだろうか?
子どもが「筋ジス」の理解を進めるのに重要な思春期前後の時期に、特別支援学校はもっと積極的に関わらなければいけないと思う。
私の経験では、高等部になって編入してくる子どもの中に自分の人生に対して敗北感を持ち、自分らしい生活の確立に投げやりの態度で終始し、正しいケア医療を継続してこなかったために身体変形や心・呼吸機能低下が著しい子どもたちをみることも多い。
もちろんここでもケア医療のレベル差は大変大きな問題であるが、特別支援教育の専門性が十分発揮されているとは思えない。このままではいけない。
|
| |
②デュシェンヌ型を中心とする筋ジスでは、思春期前後の親に対する反発心の芽生えと同時に進行性運動機能低下のため身体的には母親により濃厚に依存しなければならない。非罹患児であれば母親に対する抵抗感は空間的に離れる時間を作ることで緩和できる。
しかし、筋ジス児では、日常生活の依存度が増えるばかりであり、「離れる」ことの困難は大きい。ここでの彼らの悩みは深いと思われる。
こういった問題を考慮しての子育てが求められる。これも思春期前後に特別な支援が必要な理由である。 |
| |
③在宅生活が行われる場合は、親が一般的な子どもへのしつけと同時に筋ジスという病気の理解を促すことになる。しかし、現実には大きな困難があると思われる。「この子が不憫で」という母親の涙ながらの言い訳を何度も外来で聴いている。
一方筋ジス病棟に入院した場合には、しつけと理解への支援は教師と病院のスタッフが中心になり行う。病院には筋ジス年長児・者が居る。彼らの姿に自分の将来像を重ねるだろう。
まだ病気の理解が出来ないうちに、重症な患者の状態をみることは不自然な学び方と言わざるを得ない。加えてその病棟での振る舞い方(病棟でいい子になっておく術)を身につけると同時に、将来の夢を形作り始める。極めていびつな育ちになってしまう。自主性の目覚めによる大人への試しが、集団生活の場においてはわがままと混同される恐れがある。子どものしつけという観点からは、親ができないことをどこまで他人が行えるのだろう。
|
生活の場は、子どもの育ちを意識して決めなければならない。私たちは自分の育ちを思い出し、育て方の専門家である教師の意見を尊重し、できることを先ず行わなければいけない。
また方針を決める時には、支援する大人たちが「正しい知識」を持ち合った上で議論していく。もちろん決定後の変更も可能にしておく配慮は必要である。
|
| |
④生活のオプションを用意したうえで子どもに選択させることが必要である。少なくとも彼らは病気から離れられないわけであり、その病気は進行性の症状を呈する。
つまり「喪失の連続」とでもいうべき人生を余儀なくされる。しかし、その喪失による悲嘆を軽減し、可能性を開発し彼らなりの人生設計を行わせることが重要である。デュシェンヌ型筋ジスは比較的似た経過を取ることも多く、それぞれの年齢・運動能力に応じた医療、生活に関するオプションを記載した、いわゆる人生設計の基になる図を作るべきだと思う。
いわゆるすごろく的な図を作り提示するのも一つの方法である。 |
| |
⑤筋ジス病棟を出て、地域で生活するシステムの構築を行うことが不可欠である。
まず、出口というオプションを作り機能させることである。出口とは延びた寿命(デュシェンヌ型では以前に比べ10年以上の延命が可能になった)を活かすために、彼らが働ける・生活できるシステムを意味する。就労による収入の確保および生活できる場所(福祉共同住宅、在宅)の選択肢を多くすることを行わなければならない。
病棟を出て暮らしている筋ジス患者の問題点を明らかにしているケーススタディが報告されている13)。こういった方々の行動を理解し、共同する態度が求められる。患者会は、各地で行われている生活の選択肢を増やす運動を、先頭に立って支援しなければいけない。
もちろん進行性の疾患であるので、医療的管理が優先されるようになれば、もう一度入院生活に戻ることは可能でなければならない。幸いなことにわが国では全国26か所に専門病棟(専門的医療の供給を使命とし、長期入院が可能な医療機関)を有する。そこで行われているケア医療・生活支援レベルの格差を埋める努力とともに、地域に対するノウハウの積極的な公開・提供が急がれる。これは可能である。 |
| |
| おわりに |
先日、デュシェンヌ型筋ジス患者が心不全により亡くなった。心不全が重症化してきてベッド上安静を始めたころ、ベッドサイドで私と以下のような会話があった。
私が「明日から仕事で上京する。飛行機揺れるかな」と声をかける。「気を付けて」と彼。「お前が心配するか」とおどける私。
「そっか、お互いにだね」「そうそう」とうなずき合った。
やはり彼らはすばらしい感性を持ち、尊敬できる。この素晴らしい子どもたちを「育てる」ことのうれしさ、付き合うことができる楽しさを感じられる私たちでありたい。そうすることで今起こっている悲しみを超えていけると思う。無念を晴らせると思う。
|
| |
| |
| 文献 |
| 1)河原仁志 2005 筋ジストロフィー患者の在宅医療は大丈夫か 育療32:5-9 |
2)Kohler M, Clarenbach CF, Boni L, Brack T, Russi EW, Bloch KE 2005
Quality of life,physical disability,and respiratory impairment in Duchenne muscular dystrophy
Am J Respir Crit Care Med;172:1032-36 |
3)伊藤佳世子 2008 筋ジストロフィー患者の医療的世界 現代思想 36(3):156-70
http://www.arsvi.com/2000/0709ik.htm |
| 4)河原仁志 1999 教育・医療・保護者の連携への挑戦 育療16 :5-15 |
| 5)中島隆信 2006 障害者の経済学 東洋経済新報社 東京 p117 |
| 6)日本筋ジストロフィー協会
(ビデオ、冊子)2002 筋ジストロフィーの呼吸ケア |
|
7) 日本筋ジストロフィー協会(ビデオ、冊子) 2003 挑戦しよう!!スポーツに
|
| 8)石川悠加編 2004 非侵襲的人工呼吸療法マニュアル 日本プランニングセンター 千葉 |
| 9) 日本筋ジストロフィー協会(ビデオ、冊子) 2005あしたを信じて |
| 10)金澤一郎監、河原仁志編2007 誰にでもわかる神経筋疾患119番 日本プランニングセンター 千葉 |
| 11)河原仁志編 2008 筋ジストロフィーってなあに?(改訂第2版)診断と治療社 東京 |
| 12)石川悠加編 2008 NPPVのすべて JJNスペシャル 医学書院 東京 |
| 13)伊藤佳世子 2008 難病患者の病院、在宅、自立生活の経済状況 難病と在宅ケア14(6):8-11 |
日本育療学会
http://nihonikuryo.jp/meeting.html |
| |
|